UPS510SSとFeliSafeを利用する
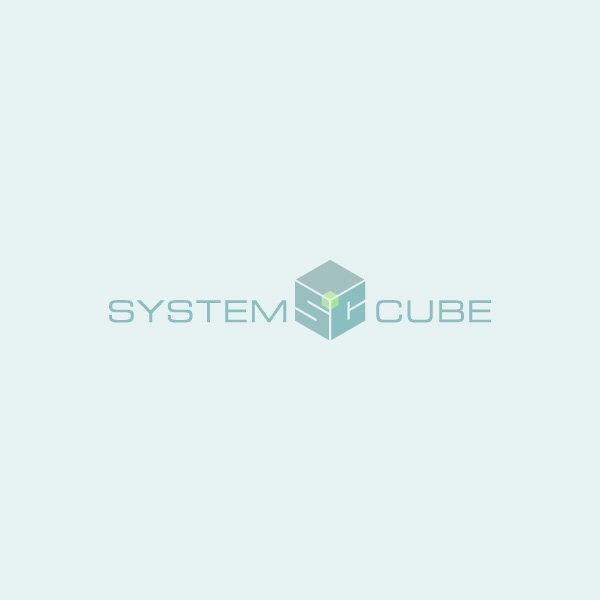
UPS510SSとFeliSafeを利用する
安価で手に入れたUPSと電源管理ソフトで、停電時のシャットダウンを設定してみました。 UPSのメーカーもさまざまありますが、ユタカ電機の常時インバータ方式のUPS510SSを利用しています。 この製品は一年前にAmazonマーケットプレイスの見切り品で約一万円で手に入れました。 現在4万円弱で販売されているので、非常にお得な買い物だったと思います。 この製品には電源管理ソフトと、通信用ケーブルがないので、別途購入する必要があります。 FeliSafe for Windows(SS、SP、ST用)をユタカ電機のオンラインストアで購入し、Windowsと接続します。 FeliSafe設定 FeliSafe同梱のシリアルケーブルをパソコンと接続します。 接続後、インストールを開始します。 接続したシリアル通信ポート(COMポート)を選択します。 FeliSafeの電源管理はサービスとして動作しますが、設定については、FeliSafeモニターを利用します。 このFeliSafeモニターが設定を変更するためには管理者権限での実行が必要とのことです。 FeliSafeモニタを実行すると、このように現在の入出力電圧や、負荷、バッテリ容量などがグラフで表示されます。 シャットダウンの設定には、メニューシャットダウンからシャットダウン設定を選択します。 電源復旧待機時間は、短時間で復旧する停電にはUPSのバッテリでシャットダウンせずに対応したくなる場合は、長くすればよいのですが、それだけUPSのバッテリを消費してしまうので、あまり長くしすぎるのも問題があります。 短時間に複数回の停電が続くと、正常にシャットダウンできない可能性もあります。 今回はつないでいる機器の総電力消費量から120秒にしていますが、一度シャットダウンを完了させるまでどれぐらいのバッテリ残量になるのかをテストしてみるとよいでしょう。 またシャットダウンプロセスが開始してから、完全シャットダウンまでの時間がどれぐらいかかるかも重要となります。 このFelisafeにはスケジュールシャットダウンとウェークアップの設定も可能なので、毎日定時間に起動とシャットダウンを行うことも可能なようです。(今回必要がなかったので、テストはしていません) シャットダウンのテストをすると、完了時でバッテリ残量が62%ぐらいとなっていました。 これで瞬間停電や、長時間の停電にも耐えることができそうです。 これから台風などが来る季節でもあり、一つ安心感を得ることができました。 特に台風の季節でなくともUPSは必要なものですが、最悪数時間の作業を失ったり、ハードウェアの故障の発生を考えれば、それほど高価な出費でもないと考えます。
